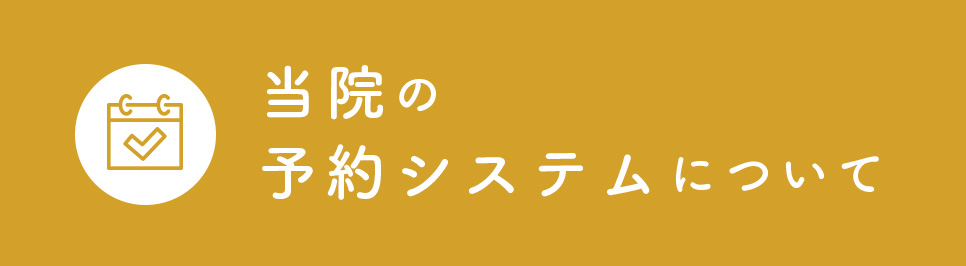おむつかぶれとは

おむつかぶれは、赤ちゃんのデリケートな肌がおむつに覆われている部分に起こる皮膚の炎症です。
医学的には「おむつ皮膚炎」とも呼ばれます。おむつかぶれは、生後3ヶ月から1歳くらいまでの赤ちゃんによく見られ、特に離乳食が始まる頃や下痢をしている時に起こりやすい傾向があります。
おむつかぶれの症状は、おしりや太ももの内側、お腹の下部など、おむつが触れる部分に赤みやぶつぶつ、ただれが生じることが特徴です。
軽度の場合には少し赤くなる程度ですが、重症化すると皮膚がめくれたり、出血したりすることもあります。
赤ちゃんがおむつかぶれになると、不快感やかゆみから機嫌が悪くなったり、夜泣きが増えたりすることもあります。
保護者の方にとっては、赤ちゃんがつらそうで心配になることも多いかと思いますが、適切なケアと治療で改善することがほとんどです。
おむつかぶれの原因
おむつかぶれにはいくつかの原因が複雑に絡み合って発生します。主な原因は以下の通りです。
1. 蒸れと摩擦
おむつの中は、通気性が悪く高温多湿になりやすい環境です。特に夏場や汗をかきやすい赤ちゃんは、おむつの中が蒸れやすくなります。
湿った状態の肌は、乾燥している肌よりも摩擦に弱く、おむつの素材や衣類との擦れによって皮膚のバリア機能が低下し、炎症が起きやすくなります。
新生児の肌は特にデリケートなので、わずかな刺激でもおむつかぶれを起こしやすい傾向があります。
2. 排泄物による刺激
尿や便には、アンモニアや消化酵素といった刺激性の物質が含まれています。
これらが長時間肌に触れていると、皮膚の表面がアルカリ性に傾き、バリア機能が壊されて炎症を引き起こします。
特に下痢をしている時は、便の回数が増えるだけでなく、便中の刺激物質も強くなるため、おむつかぶれが悪化しやすくなります。
3. カビ(カンジダ菌)の増殖
おむつの中の高温多湿な環境は、真菌(カビ)の一種であるカンジダ菌が増殖しやすい条件でもあります。
通常の皮膚にも存在しているカンジダ菌ですが、皮膚のバリア機能が低下しているところに増えすぎると、カンジダ性おむつ皮膚炎を引き起こします。
おむつかぶれが長引いたり、一般的なおむつかぶれの薬ではなかなか治らない場合は、カンジダ菌が原因である可能性も考慮する必要があります。
おむつかぶれとカンジダの見分け方は、おむつかぶれの場合、おむつの当たる部分全体が赤くなることが多いのに対し、カンジダの場合は、赤い斑点や水疱の周りに白いカスのようなものが付着したり、皮膚のひだの部分に症状が強く出たりすることがあります。
4. その他
石鹸の洗い残しや、おしり拭きの成分、特定の衣類へのアレルギー反応などが原因となることも稀にあります。
また、抗生剤を服用していると、腸内細菌のバランスが崩れて下痢をしやすくなったり、カンジダ菌が増えやすくなったりして、おむつかぶれが悪化することがあります。
おむつかぶれの症状
おむつかぶれの症状は、その重症度によって様々です。
| 重症度 |
症状の具体例 |
| 軽度 |
おむつが当たる部分にうっすらと赤みが出る。
ぶつぶつやただれはほとんど見られない。 |
| 中等度 |
赤みがはっきりしてくる。皮膚の表面がガサガサしたり、小さなぶつぶつ(丘疹)ができたりする。
かゆみや不快感が増してくる。 |
| 重度 |
赤みが非常に強く、皮膚がただれたり、ジュクジュクしたりする。皮膚の表面がめくれ、出血を伴うこともある。
痛みやかゆみが強く、赤ちゃんが不機嫌になる。
さらに、カンジダ菌が二次感染を起こしている場合は、赤い斑点の周りに白いカビのようなものが付着したり、皮膚のひだが深く赤くなったりする。 |
症状がひどくなると、赤ちゃんは排泄のたびに痛がったり、おしりを拭かれるのを嫌がったりするようになります。また、夜泣きが増えたり、食欲が落ちたりすることもあります。
特に、ぶつぶつが水ぶくれになったり、膿を持ったりする場合は、細菌感染を併発している可能性もあるため、早めに医療機関を受診することが大切です。
おむつかぶれの治療
おむつかぶれの治療は、ご自宅でのケアが基本となりますが、症状が改善しない場合や悪化する場合には、病院での診察と適切な薬による治療が必要になります。
ご自宅でのケア
- 清潔に保つ
おむつが汚れたらすぐに交換し、おしりを優しく洗い流すことが最も重要です。シャワーや洗面器にお湯を張って、刺激の少ない石鹸で優しく洗い、十分にすすぎます。ゴシゴシこすらず、手のひらでなでるように洗うのがポイントです。おしり拭きを使う場合は、摩擦刺激を避けるため、優しく押さえるように拭き取りましょう。
- しっかり乾燥させる
洗った後や拭いた後は、清潔なタオルで水分を優しく吸い取り、しっかり乾燥させます。自然乾燥が一番ですが、時間がない場合はドライヤーの冷風を少し離して当てるのも効果的です。ベビーパウダーの使用は、毛穴を詰まらせたり、かえって刺激になったりすることがあるため、あまりおすすめできません。
- 保湿と保護
乾燥した後は、ワセリン(プロペト)や亜鉛華軟膏などの保護剤を塗って、皮膚に薄い膜を作り、尿や便の刺激から肌を守ります。亜鉛華軟膏は炎症を抑える作用もあります。これらの保護剤は、おむつ交換のたびに毎回塗布しても問題ありません。
- 非ステロイド性抗炎症薬
軽度のおむつかぶれや、ステロイドの使用に抵抗がある場合に、アズノール軟膏やスタデルム軟膏などの非ステロイド性の軟膏が処方されることがあります。これらは炎症を抑えつつ、皮膚を保護する作用があります。
- ステロイド外用薬
炎症を抑える目的で、ロコイドやリンデロンなどのステロイド軟膏が処方されることがあります。ステロイドと聞くと心配される保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、医師の指示通りに適切な期間、適切な量を守って使用すれば、高い効果が期待でき、安全性も高い薬です。おむつかぶれが重症の場合には、ステロイド外用薬が効果的です。
- 抗真菌薬
カンジダ菌による感染が確認された場合は、カビを抑える抗真菌薬が処方されます。おむつかぶれとカンジダを併発している場合、ステロイドと抗真菌薬を併用することもあります。おむつかぶれが治らないと感じたら、カンジダ感染の可能性も考えて、受診をおすすめします。
- 市販薬
ドラッグストアなどで市販されているおむつかぶれの薬もありますが、症状が重い場合や、カビによるものと見分けがつかない場合は、自己判断せずに受診することをお勧めします。市販薬の中には、亜鉛華軟膏配合のものや、非ステロイド性の軟膏などがあります。
当院では、おむつかぶれについて詳しく説明しますので、不明な点があれば遠慮なく質問してください。
ご自宅で気をつけること
おむつかぶれを予防し、悪化させないためには、日頃からのご自宅でのケアが非常に大切です。
1. こまめなおむつ交換
尿や便がおむつの中に長時間滞留するのを防ぐため、おむつが汚れたらすぐに交換しましょう。
特に新生児は排泄の回数が多いため、こまめなチェックが必要です。排便後は必ずおしりを洗い流す習慣をつけましょう。
おしり拭きだけで済ませるよりも、洗い流す方が肌への負担が少なく、清潔を保てます。
下痢の時は、いつも以上におむつ交換の頻度を増やし、おしりを洗い流す回数を増やしましょう。
2. おしりを清潔に保ち、しっかり乾燥させる
排泄後は、ぬるま湯で優しくおしりを洗い流しましょう。
石鹸を使う場合は、刺激の少ないベビー用石鹸を選び、泡立ててから優しく洗い、十分に洗い流してください。
洗い残しは肌トラブルの原因になります。洗った後は、清潔な柔らかいタオルでポンポンと押さえるように水分を拭き取り、完全に乾くまで時間を置きます。
おむつを履かせる前に、おしりの状態をよく確認し、乾いていることを確認しましょう。
可能であれば、おむつを外して数分間、おしりを空気にさらして乾燥させる「おしり乾燥タイム」を設けるのも効果的です。
3. 保護剤の活用
おむつ交換のたびに、ワセリンや亜鉛華軟膏などの保護剤を薄く塗る習慣をつけましょう。
これは、尿や便がおしりの皮膚に直接触れるのを防ぎ、バリア機能の低下を抑える効果があります。
特に、おむつかぶれが改善してきた後の再発予防にも有効です。
プロペトは純度の高いワセリンであり、肌への刺激が少ないため、新生児から安心して使えます。
4. おむつ選びとサイズ
おむつの素材やサイズも、おむつかぶれに影響することがあります。
通気性の良いおむつを選び、赤ちゃんの体型に合ったサイズを選ぶことで、蒸れや摩擦を軽減できます。
きつすぎるおむつは摩擦の原因になり、大きすぎるおむつは隙間ができて漏れやすくなり、かえって肌が汚れてしまうことがあります。
5. 症状に合わせた適切な対応
「おむつかぶれかな?」と思ったら、早めに対策を始めましょう。軽度のうちにケアを始めることで、重症化を防ぐことができます。
しかし、ご自宅でのケアを続けても症状が改善しない場合や、悪化しているように見える場合は、迷わず小児科を受診してください。特に、ジュクジュクしている、ぶつぶつがひどい、広範囲に広がっている、高熱があるなど、全身症状を伴う場合は速やかに受診しましょう。
おむつかぶれとカンジダの見分け方は難しいこともあり、自己判断で市販薬を使い続けると悪化させてしまう可能性もあります。
医師の診察を受けて、適切な診断と治療を受けることが、赤ちゃんを早く楽にしてあげるための一番の近道です。
当院では、お子様の肌の状態を丁寧に診察し、ご家庭でのケア方法や適切なおむつかぶれの薬について詳しくアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。
お子様のおむつかぶれは、保護者の方にとって大きな心配事の一つかと思います。
しかし、適切な知識とケアで、ほとんどのおむつかぶれは改善します。
もしご不安なことがあれば、いつでも当院にご相談ください。お子様が快適に過ごせるよう、一緒にサポートさせていただきます。